『欧州のCircular Economyの動向』(2016/3資源素材学会)
1.はじめに
今世紀末には循環型の資源利用が必須となるなかで、EUはその経済活性の手段としても2015年12月欧州委員会からCircular Economyに関して、Circular Economy Strategy : closing the loop – An EU action plan for the CIRCULAR ECONOMYと題するアクションプランを発表した。これはEUの中期計画Horizon2020の7つのフラッグの一つである資源効率(Resource Efficiency)の具体化の試作であり、このアクションプランはそれに基づく法改正をEU諸国に要求するものであり、EUはその方向に踏み出したといえる。 CIRCULAR ECONOMYという表現が日本でいう「循環型社会」と類似しているために、国内では「欧州が循環型社会を再評価している」との表面的な理解が多いが、本発表では、このアクションプランの分析および昨年秋の国際資源フォーラムでの議論を通じて、EUのCircular Economyの本質について論じ、特に我が国の循環型社会づくりとの相違を明らかにする。 また、Circular Economyのなかでもsustainable secondary resource managementが注目され、国際標準期間を使った動きが起こっており、それに対して「健全で責任ある国際資源循環」とは何かについても論じる。
2.Circular Economyとは
まず、EUの打ち出しているCIRCULAR ECONOMYを、その基本文献に立ち返って見てみよう。アクションプランそのものは、表1のような項目を並べている。
表1 CIRCULAR ECONOMYの廃棄物法規制改正アクションプラン
|
ここだけを見ると、廃棄物処理に関する法規制の強化のように受け取れる。しかし、これはマテリアルフローの出口という法規制的にわかりやすい部分に対して定量的な目標づけを加盟国に促すものであり、特に「埋め立ての禁止」はこれまでの欧州の廃棄物処理のあり方を一変させる方向であって、それにより埋立で終焉していたマテリアルフローを循環に変更させる大きなドライビングフォースとなる。また、「リサイクル率の定義」はそれを用いるEcodesignやグリーン公共調達に大きく影響を与えることになる。
そのような新たなマテリアルフローやその中でのエコデザイン、グリーン調達などの流れにこそ最終的にCIRCULAR ECONOMYが目指すものがあり、これはこのアクションプランとともに出された「COMMUNICATION FROM THE COMMISION TO THE EUROPEAN PAELIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGION – Closing the loop — An EU action for the Circular Economy」 (以降 Closing Loopと呼ぶ)に期されている。CIRCULAR ECONOMYの本質を見るには、アクションプランではなくこのClosing Loopを読み解くべきである。
Closing Loopの文書があまり日本では注目されないのは、これがLife-cycle thinkingをベースにした包括的公正であるために、総花的幹事を受けさせるからであろうと思われる。しかしそのLife-cycle thinkingに持ちづいた構成をもっているゆえにこの文書とそれが提起しているものは重要なのである。表2にその構成を見てみる。
| 表2 Closing Loopの構成
1 production 2 Consumption 3 waste management 4 from waste to resource 5 priority area 6 Innovations, investment, and other horizontal measure 7 Monitoring progress towards a circular economy |
Productionでは、デザインのフェイズと製造プロセスが、資源使用と廃棄物の発生に影響を与えるとして取り上げられている。1.1 Product Designでは表3の内容が強調されている。 (色付け、下線は筆者)
表3 1.1 Product Design
– 欧州委員会は、相異なる一連のCIRCULAR ECONOMYへの寄与でのプロダクトポリシーの取り組みのより整合性のあるフレームワークのアクションと展開を行う。 |
ここでエコデザインの要素として、修理可能性、アップグレード可能性、耐久性、およびリサイクル性が取り上げられており、それらが製品要求として進められることが掲げられている。ここに上げられているEcodesign Detectiveは2009年に生体されたもので、日本では有名無実感を持って受け取られているケースが多いが、ここにも期されているEcodesign Working Plan for 2015-2017では、「エコデザインは省エネルギーの面で成功した。これを資源効率や他の環境側面に拡大していく」ととらえており、エネルギー効率にRohsやREACH,、なども統括する枠組みにしようとして、あらゆる製品をどの環境側面が問題になるかという視点で再点検し、エコデザインの方向性を出している。そこで、CIRCULAR ECONOMYという視点で上からかぶせられるのが、修理可能性、アップグレード可能性、耐久性、およびリサイクル性であり、例えば銃声のエコデザインの成果であったエネルギー効率の良い製品も、その生の意の持続性、耐久性という視点がかぶさってくることになり、有害物質の使用・管理もリサイクル性という視点がかぶせられる。
表4 1.2 Production Process
-欧州委員会は、産業共生を促進しEU横断的な公平な土俵の創生を援助し、副産物に関するルールを明確にするための提案を、廃棄物に関する法改正提案の中で、行う。 |
Production Processの環境影響や資源消費は日本では大きいが、EUでの記述は思ったより小さい。副産物利用の産業共生をうたっているところは評価されるが、それ以外は技術的裁量手段(Best Averrable Technique)の参照文書の提供にとどまり、産業共生に関しても副産物ルールの明確化ていどであり、他の項目のような推奨策や規制などの能動的な対応があまり気されていないのが特徴である。
| 表5 2 Consumption
– 欧州委員会は、エネルギーラベリング施策での耐久性情報と同様に、エコデザインにおいて、特に耐久性(durability)および修理やスペアパーツ情報の有効性にかかわるバランス良い要件について配慮する。 - 改定された廃棄物提案において、欧州委員会はリユースのアクティビティを奨励する新たなルールを提案している。 - 欧州委員会は、具体的な製品にかんする保証のよりよい強化への作業と、改善のための可能なオプションの調査を行うとともに、偽のグリーン主張に対して立ち向かう予定である。 - 欧州委員会は、プランの陳腐化にかかわる問題を見出すために、H2020のもとで独立のテスティング プログラムを準備する。これには関連するステークホルダーが必要に応じて参加する。 - 欧州委員会は、グリーン公共調達(GPP: Green Public Procurement)に関して、新規もしくは改定された基準にCIRCULAR ECONOMYの視点を強調することにより、GPPのより多くの採用のサポートとEUファンディングと自らの調達に置ける率先した例示でアクションをおこす。 |
一方で、Consumptionに関してはClosing Loopは雄弁である。
ここでもecodesignの要件、耐久性や修理可能性が強調されており、さらにリユースが強調されている。またグリーン調達に対してアクションを起こす意気込みを示すなど、基本的にこの消費段階でのリユースや修理などの素材時限までおとさない製品フローを形成することにCIRCULAR ECONOMYの力点があることがわかる。
表6 3 廃棄物マネージメント
– 欧州委員会は、加盟国とその地域で廃棄物セクターでの結束政策投資がEUの廃棄物法制度に寄与しEUの廃棄物序列に基づくものであることを確認することを支援する。 |
アクションプランでは冒頭に目標が掲げられた廃棄物マネージメントは、思ったより記述が簡単である。これはすなわち、廃棄物処理を改善することよりも、廃棄物の発生を防ぐことにCIRCULAR ECONOMYの力点があり、廃棄物発生処理コストやそれに対する投資を発生防止に振り向けることに重点があるからである。そして書かれていることもリサイクル目標やその計算方法、定義の明確化であり、リサイクルによる廃棄物の減量化が主たるターゲットになっている。その意味では、廃棄物処理場の不足が循環型社会へのモチベーションになった我が国の進め方に類似してはいるが、逆に、埋め立ての余地を残すヨーロッパがなぜ埋立からの脱却を図ろうとしているのかを見ておく必要がある。
| 表6 4 廃棄物から資源へ
- 欧州委員会は、必要とされる二次資源(secondary raw materials)、特にプラスチック、に対する品質基準を整備する作業を発足させる。また「end-of-waste」に関するルールの改善の提案を行っている。 - 欧州委員会は、単一マーケットでの有機もしくは廃棄物ベースの肥料の承認を容易にするために、肥料に関するEU法規の改定を提案する予定である。それによりCIRCULAR ECONOMYでのバイオ栄養物(bio-nutrients)の役割をサポートする。 - 欧州委員会は水のリユースをやりやすくするための一連の行動を起こす。これには、たとえば灌漑や地下水利用に対して再利用水を使う場合の最小要件に関する法規的提案も含まれる。 - 欧州委員会は、いかに製品中の化学物質の追尾を改善しいかに存在を減少させるかを含む、化学物質と製品と廃棄物の法規の間のインターフェイスにかかわるオプションを分析し提案する予定である。 - 欧州委員会は、さきほど立ち上げられたRaw Materials Information Systemをより発展させ、EUワイドの原料マテリアルフローに関する研究をサポートする。 |
そこで注目されるのが「廃棄物から資源へ」の部分である。二次資源特にプラスチックに関する品質保証の整備が明示されているが、金属に関しても後述する二次資源マネージメントの規格化の動きがあり、プラスチックを先頭に掲げつつ多くの分野で基準化が進められるものと予想される。また、バイオマスや水の再活用も取り上げられており、特にバイオマスは、食物とともに後の重点領域でも取り上げられている。また、化学物質規制がこの「廃棄物から資源」の中で取り上げられていることも、従来の製造段階の管理から一歩出たLife-cycle thinkingやサプライチェーン・マネージメントの方向付けが強まっているとみてとることができる。そらに、それらを総見するマテリアルフローに関する研究が、このようなフェイズで盛り込まれていることは、日本のアカデミーはもっと注目する必要があるだろう。
これらを遂行する上での優先領域が5つ挙げられているが、ここではプラスチックとcritical raw materialについてのみみてみる。
| 表7 5.1 Plastic
- 欧州委員会は、リサイクル可能性や生分解性、ある種のプラスチック中の有害物質、および海洋ごみの問題に取り組みつつ、CIRCULAR ECONOMYの中でのプラスチックに対する戦略を導入する。 - 欧州委員会は、廃棄物の法規改定提案の中で、プラスチック容器・包装のリサイクルのより野心的なターゲットを提案している。 |
記述は単純である。しかし、EUがこれらの物質の回収とリサイクルに本腰を入れだしたのは間違いない。2015年の10月にスイスのダボスで行われた国際資源フォーラム2015では、議論はほぼCIRCULAR ECONOMY一色であったが、特にプラスチックに関しては、プラスチックの成分設計の段階から議論がなされ、リサイクル製品の品位の工場のみならず、「有害物質を含まない」からさらに進んで「有害性のない成分で」プラスチックを製造することが議論され、科学の役割が強調されていた。
| 表8 5.3 Critical raw Material
– 欧州委員会はレアメタル(critical raw materials)の回収を奨励する一連のアクションを行い、さらなるアクションに向けたベストプラクティスとオプションを含むレポートを作成する。 - 欧州委員会は、加盟国による廃棄物に関するこの問題に関する改定提案へのアクションを奨励する。 |
またCritical raw materialについては、同じく国際資源フォーラムではcriticalityの定義についての議論が行われるとともに、持続可能な二次金属のマネージメントのガイドラインが議論されており、これらは単に欧州の基準だけでなく国際基準として展開されることが予想される。
なお、Closing Loopは、6.Inovation,Investment, and other horizontal measuresでHorizon2020の2016-2017のプログラムにIndustry2020として650ミリオン€のファンドを盛り込むことや、投資の促進をうたい、7.Monitoring progress towards a circular EconomyでResource Efficiency ScoreboardやRaw Materials Scoreboard を考慮するなどモニタリングの重視などを述べている。
3. Circular Economyに対する考察
まず、EUの掲げるRE,CIRCULAR ECONOMYの背景を見ておこう。REは単独で出で来たものではなく、2008年のリーマンショックで金融業を中心に打撃を受けたヨーロッパがその経済活性を求めて建てた戦略Europe 2020の一環として打ち出されたものである。
Europe 2020は、” A strategy for smart, sustainableand inclusive growth”をかかげ2011年に打ち出された”7 flagship Initiatives”のひとつである。これは、リーマンショック以前dematerialization等のコンセプトを打ち出しソフト化させることで成長していた経済が打撃を受けたことに対して、より頑強な成長戦略をとるためのものであり、経済が社会的状況や環境負荷の悪化を随伴して成長しない、いわゆるdecouplingを目指している。そこでは、なんといっても新たな雇用の創出が目標とされ、その課題対象として環境、エネルギー、貧困の防止が謳われている(図1)。

これは環境、エネルギーなどの問題解決自体を優先した課題設定というより、経済活性化の新領域として、環境や貧困対策を掲げているとみるべきであり、dematerializationで進めてきた経済のソフト化の流れをパワーエコノミーの下でコントローラブルではなくなりつつある金融の方向ではなく、新たな産業形態の創出に向けての動きであると見ておくのが妥当である。
それを考慮すると、REを素材産業など直接資源にかかわる産業が相対的に脆弱なヨーロッパが掲げる理由も見えてくる。すなわち資源問題そのものがヨーロッパ経済に対して打撃を与える可能性があるからREを唱えるのではなく、消費の立場から資源効率的な運用を提唱しそのためのシステムを組むことによって、そこに新たな産業と雇用の機会を求めようというのである。

しかしREだけでは、実際に資源や素材を扱うことの少なくなったヨーロッパでは具体的経済行為に結びつけることが難しい。そこで打ち出されたのがCIRCULAR ECONOMYであり、REのヨーロッパ的実践的明確化であるといえる。
REの特長をよく表しているのは、図2に上下で示す2014年4月の”Circular Economy Europe”で比較されている二つのマテリアル・フローである。資源を循環させ廃棄物の減量を目指す立場からは、図2の上図でも十分には「循環型社会」を描いた図であるともいえる、しかしEUではこれをlinear economyと称し、ここから脱却してCIRCULAR ECONOMYに向かわねばならないとしている。この違いは何かというと、CIRCULAR ECONOMYは単にマテリアルを循環させることではなく、循環のプロセスのあちこちにビジネスチャンスを形成することをこそ目的としているからである。もちろん、そのような多様なパスが発達しネットワーク的に資源循環が進むことは循環の効率化にとっても有効なことであり採用に値するが、ここではまずその主客、目的と手段が転倒していることを見ておく必要がある。
その典型的なものが”Circular Economy Europe”で多くのページを割いて展開している、循環形成のバリアである。世界中いずれもいまだ循環型社会形成が不十分で、そこに多くのバリアが存在していることは事実である。しかし、この”Circular Economy Europe”では、そのバリアを示しつつ、その問題の根源を分析し突破する道筋を検討するのではなく、そのバリアを迂回する道、すなわち新たなビジネスチャンスを見出す道をもっぱら示している。すなわち、「モノは廻すものではなく廻るもの」であり、その廻る過程をいかに有効に活用し経済活性に結びつけるかがCIRCULAR ECONOMYの主眼であると見ておく必要がある。

日本の循環型社会は、廃棄物減量の循環を形成するために消費者、リサイクラー、製造者が役割分担して問題解決にあたるシステムである。それに対して基本的に、ヨーロッパのCIRCULAR ECONOMYにはproduceは無視されている。モノは消費し循環するものであり、その循環過程に新たなビジネスを多重に張り巡らそうというのがCIRCULAR ECONOMYの基本方針である。そのビジネスの多重なネットワークはアフリカにも及んでおり、アフリカ内にはびこるinformal sectorに対して、EUルールに基づくformal recyclerとそのネットワークビジネスが参入するチャンスとしようとしている。そして、そのマテリアルフローの受け皿になるのがリサイクル・メジャーである。製品は生み出すものではなく入ってくるものであり、中国や韓国などの製品プロデューサーに対しては生産者責任として、material taxやプラスチック添加物など循環を阻害するものに対する無含有などの製造者責任が問われるが、従来叫ばれたような拡大製造者責任ではなく、そちらは循環物のバリューチェーンとして展開する。その中で新しい産業や価値を生みだそうとするのがCIRCULAR ECONOMYであり、日本が現行経済の枠の中で循環システムの構築を目指すのに対して、「循環に付加価値をつけ」た新たな経済システムの構築への挑戦が欧州のCircular Economyであるとみるべきである。
4.持続可能な二次金属マネージメントのガイドライン
この動きのひとつとして持続可能な二次金属マネージメントのガイドライン作りがある。これは、図4のように拡大製造者責任に対する資源の側からの適正評価を意図して検討されているものである。特徴的なことは、ISOのWorking group Agreementという手続きをとって議論されているところである、IWAはそのワーキンググループの参加者のみの合意で成立する。これまではIWAで議決された内容に基づきTWAなどが作られてISOの標準化に向かったが、この場合はISO標準の作成を目指さず、IWAのみでISOの手続きに基づいた合意形成としてのガイドライン原則を作成し、それをもとに民間機関が「持続可能な二次金属」マネージメント」の認証を行う、デファクトスタンダード化が意図されている。

内容はリサイクル自体よりも、雇用・労働条件の適正化、法律の順守、周辺環境の配慮など、一般の企業として当然のことがより多く盛り込まれている。これは、主としてヨーロッパの問題意識がアフリカのE-waste問題に向いており、その現時点でのインフォーマル・セクターに対して、ヨーロッパと正規に取引できるイクイバレント・パートナーを求めており、このガイドラインはそのための認証に使おうとする意図が読み取られる。そうした場合、実際のe-waste問題の解決やリサイクルの促進は光景に追いやられる。現に現時点での案がパブリックコメントにかけられているが、リサイクル率の向上や、リサイクルにとって本質的な問題である発生廃棄物の処理に関しては、独立した項目はなく、トレーサビリティのなかで読み取るしかない構造になっている。この発生廃棄物(不要物)の取り扱いがリサイクルにとって最も重要であるという認識は、これまで埋め立てを容認できていた欧州にとっては発想的に致命的に欠落した部分である。ヨーロッパにおけるE-wasteの発生もアフリカに置ける発生も、図5に示すように、基本的には不要物の処理の欠如に起因している。現在検討されているガイドラインでは、この日本流に言うとゼロエミッションの発想が欠落しているのである。

- 今一つの問題は、リサイクルの抽出プロセスの単純なとらえ方である。これは欧州には巨大な二次金属抽出業者がありそこに運び込むまでが他の経済主体の行為であるために、抽出プロセスについて言及する必要が弱いことに起因していると思われる。しかし、それゆえに、リサイクルの効率的創業のための天然鉱石との混合使用やそれによる廃棄物処理の合理化などについての努力が全く評価されない形になっている。それだけではない、それがトレーサビリティとかかわるとき、リサイクル物である保証が極めて厳しい要求となる。
| 表8 IWAガイドライン中の「トレーサビリティ (カスドデイ(管理証券)のチェーン: CoC) – CoC展開の三つのモデル」
– 物理的隔離 : 金属を含む廃棄物もしくは、由来が明示されかつGP(Guidance Principles)に準拠(compliance)する二次金属の出荷品(consignments)は、他の廃棄物出荷物や由来不明の二次金属、一次金属と物理的に隔離される。 - マスバランス: 由来が明示されかつGPに準拠する二次金属の出荷品は物理的に他の二次金属や一次金属と混合される。 入ってくる(entering)物質の証拠書類(Documentation)はGPに準拠しない二次金属の量がGP準拠の二次金属の量を超えないことを確認する。 - 帳簿(Book)と主張(claim): GP準拠の経済担当者(economic operators)は、証書(certificates)をつくり専用の(dedicated)プラットフォームで取引することができる。二次金属を用いる製品製造者はそのような証書を買いその件にかかわるGP準拠を主張することができる。 |
表8にそれを示したが、物理的隔離では100%使用済み由来でないといけないことになり、日本の製錬業のリサイクルは全く認証対象とされなくなる。二番目のマスバランスにおいても、天然鉱石などがリサイクル由来を超えてはならず、これもまた多くの日本の製錬業のリサイクルを対象外とすることになる。これは製錬業だけの問題ではない。先に見たエコデザインで製品への高いリサイクル率が求められた場合、リサイクル率の定義で、「持続可能な二次金属マネージメントに認証された企業のトレーサブルな数値に基づくこと」などと記載された場合には、天然鉱石とともにリサイクルしている精錬会社の銅から製造した銅線はリサイクル率からはずされ、それを搭載している電子機器や自動車も実際はリサイクルベースの素材で製造しているにもかかわらず、非エコデザイン製品として排斥される危険性を有している。
さらに、このようなリサイクルプロセスを考慮に入れない定義は、日本と同じくモノづくりを志向するアジア諸国においても、製造とリサイクルを分離させ、「電子基板など発生廃棄物は自国で処理せずヨーロッパに持っていけばよい」という方向付けになる危険性も副名でいる。このように、製造を外に置いた使用段階以降の循環を考える欧州のCircular Economyは真の循環型社会の形成に対して大きな不十分性を持っており、欧州の動向をウォッチやキャッチアップさらには対処するのではなく、それに対置するような健全な国際資源循環のビジョンを積極的に打ち出すべきである。
5. まとめ
欧州のCircular Economyは循環型社会の構築のためのソリューションを与えようとするものではなく、循環するプロセスに新たな付加価値を与えて経済活性を図る経済政策である。そのために現行経済の枠組みの中で理解しようとするとその意図や挑戦性が見えなくなる。また、モノづくりの視点が欠如している故に、日本やアジアでの物質循環モデルとは大きく異なった構図が想定されており、これがグローバル化される前に、モノづくりを前提にした健全な国際資源循環をめざす動きを強めていく必要がある。
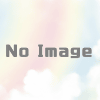
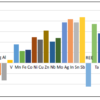


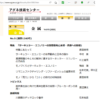
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません