実は大きく変わったEUの2022EcoDesign枠組み
(末尾にディスカッション欄あり)
2022年3月にこれまでのエコデザイン指令(2009)を廃して新たにエコデザイン要件枠組みを設けることが発表されました。
国内の論調では、エコデザイン要件は、従来のものとあまり変わらず、①対象が全製品に広がること、②製品パスポートが導入されること、に視点が行っていますが、実は、2009年指令と2022年枠組みでは、大きな変化が起きていることがほとんど気づかれていません。ここてはその問題を指摘したいと思います。
製造者主体から多様な経済行為者へ
大きな変化とは、2009年指令では「製造者が環境性能に優れた製品をいかに市場に出すか」ということが指令の中心だったのですが、2022年枠組みでは、ディストリビューターやディーラーが環境性能主張を効果的に行い経済活性につなげるために何が必要かという視点に変わっているということです。
これを図にすれば、次のようになります。

極論すれば「製造者責任からの脱却」と言ってよいほどの大きな変化です。これは2022枠組みに至る議論の中でも、欧州議会調査局のエコデザイン指令の実施評価 の政策提言で「(…)エコデザインプロセスにおいて、製品だけでなく、その機能に必要なシステム全体を考慮することは、資源効率に向けたもう一つの重要な成功である」などと指摘されており、製造者が製品を市場で売るという行為が経済行為の中心でありそこを改善することが持続可能性へのシフトに繋がるという考え方から、製品がサービスとして機能するところにポイントがありそこの経済主体が環境行為を行いやすくするためにどのようなデザイン要件や情報要件をつれるか、という視点に変わっているということです。extended producers responsibilityという表現は使用されていますが、そのresponsibilityが日本語で言う「責任」、すなわち製造者がすべてをかぶるというイメージから、「応答性」とでも訳すべき担う主体ではなく役割の一翼としての関与性であるという見方に変わっているということです。これはパプコメの中でも「製造者にresponsibilityがあるのだから、環境サービス市場における経済メリットのフィードバックを受けられるようにすべきだ」などという主張ともあいまったものです。
先の図に戻ると、緑の矢印の部分が、2009指令および2022枠組みで強く意識されている環境に関わる経済行為の部分です。いうならば、2009年指令では家電メーカーが頑張ってエコ製品を販売していたが、2022枠組みでは例えばアマゾンがエコ製品を扱うことが多いという事実に対応するエコデザインとはなにか、ということを追求しているといえます。
これは、我が国を例としても消費市場構成の次の図を見るとその理由がわかります。

つまり、消費者購入市場は157兆円あるのに対して、家具家事用品自動車などの耐久財(スマホ入る)の市場は10兆円に過ぎないのです。ちなみに、衣料は4.9兆、家賃以外の家屋関係は5.4兆で、これらは「すべての物理的製品をおおう」ための代表的な領域として建築、繊維として取り上げられています。
つまり、消費者は耐久財の購入より他の部分に多くの金銭を使っており、その経済行為に環境競争力を持ち込むには、製造者しか目が行っていなかった2009指令では不十分だから新たな枠組みが必要になったということです。ですから細かい要件はあまり変える必要はなかったともいえます。
この違いが読めていないのが日本の製造業で、あつくで製造業中心の視点で2009と2022の変化を捉えよとするから、「要件は延長線」「製品パスポートぐらいが新しい」などという見方になります。これは、EUのバブコメに寄せている意見でみても日本からのものだけが浮いている大きな理由です。海外の製造業は、パプコメの場まで使って製造業の貢献メリットを自らにフィードハックする主張をしていますが、日本からのものは、全部製造者に押しかかってくると過剰に責任を持った視点で書かれています。
製造者の性能ベースの市場競争から需要者の使用価値ベースの市場競争へ
2009指令から2022枠組みのもう一つの大きな変化は、製品性能に対する考え方です。

2009指令の時点では、「市場は性能価値で競争となるが、環境価値は競争の判断にはなりえていない」と現状を認識し、せめて同じ性能価値なら環境価値の違いが市場で優位に働くため、としてエコデザインによる製品の差別化ょ打ち出していました。しかし、2022枠組みでは、性能を明示することや製品パスポートにおける性能の記載、などが盛り込まれています。これは製造者→市場の競争が製品の性能価値で決まる時代が終わり、製品を使いサービスを売るサービス提供者とその需要者の使用価値で市場競争が行われていく、という変化をつかんでいからと思われます。つまり、サービス需要者との間では性能ではなく使い勝手が主たる競争になり、そのためには性能は決定要因ではなく必要な情報事項に役割を変えるということになります。(なお、直接2022枠組みには書かれていませんが、repair性などの言及から残存価値というタームも図には入れておきました。)
こうしてみると、「エコのために製造業が頑張らねば」として作ったのが2009指令で、「エコの主要な現場は需要者と面するサービスで、製造業はそれを支えるために何をすればよいのか」と、製造業の責任を軽くし、その製品を用いてサービスを生み出す経済行為者に重点を変えさせるのが2022枠組みと見ることもできます。
製品パスポートは製造側の重荷ではなく武器
この視点で問題にされる製品パスポートを見ると、それは製造者への義務の側面よりも、製造者の機能・環境主張をサービスの経済行為者に認識させ、そのフィードバックを得るためのインターフェイス・ツールであるという接キュク的側面が見えてきます。もちろん、パスポートの具体的記述項目がある特定地域の産業にとってのみ優位なものになった場合は他の経済競争者は不利になりますが、現時点では、製品ごとに行うべきかセクターごとに行うべきかなどが議論されている段階で、さらにエコデザイン要件についても、エコデザイン。フォーラムを関係するステイクホルダーでバランスを取ってつくり、そこで
①エコデザイン要求事項の作成
②市場監視メカニズムの有効性の検討
③自主規制措置の評価
を行うことになっています。つまり「まだ準備ができておらず、自己規制が先行してそれが機能しているのを監視しながら全ステークホルダーの合意できるエコデザイン要求をフォーラムというまだ無い組織から準備してお見なう」と書いてあるのです。
すなわち、素材や製品をB2Bで経済行為者に渡すメーカーは、製品パスポートの趣旨に沿う性能と環境パフォーマンスを、まずは自己流パスポート・プロトタイプとして経済行為者と最終需要者に渡す情報媒体を作成し先行して展開していくことが求められているのです。
では、その製品パスポートに記載する要件とはなにかですが、それは2022枠組みでは、以下のような曖昧な記述にとどまっています。(より具体的なものはフォーラムが各インダストリーの実践を踏まえて決めていくのでしょう。)

お気づきのように、ここにはフットプリントやLCA、さらには懸念物質に関してのmustの記述はありません。二番目の項目にある、エンドユーザーが環境パフォーマンスを実践する際に必要となる情報とそのための性能情報が求められています。実績ある日本の多くの素材や製品の製造業ならば比較的容易に応え先行できるものではないでしょうか。
エコデザイン2022枠組みはサービサイジング視点でのデザイン要求
このように、エコデザイン2022枠組みを、従来のリニアな製造業を経済の主役と見る2009指令と同じ視点ではなく、サーキュラー・エコノミー(決して「循環経済」ではない)的な脱リニア、脱モノ売り儲けの視点で見ると、その変化がよくわかります。多分、「すべての物理的製品」を対象としたエコデザインという名でこの分野への枠組などが提示されるのはこれが最後かもしれません。今後は、「サービスのデザイン」などデザイン概念がどこまで拡張できるか、などの視点で見直し進化が進んでいくものと思われます。
その変化が捉えられずに、20世紀型のモノ売り市場に環境価値を付加してときにはそれを非関税障壁に使う、といった発想でしか捉えていないと歴史の孤児として世界に取り残されていくでしょう。
そうならないために、一応私の気づいた、それ以外の変化をいくつか箇条書きでまとめておきました。必要なら、それ個別にも議論をしていきたいと思っています。






文責 原田幸明 CE・MVC研究会代表、SusDI代表理事
関連 簡易和訳情報
エコデザイン2022枠組み 本文
エコデザイン2022枠組みとSustainable productsに関する影響評価
エコデザイン2022枠組みとSustainable productsに関する全パブリックコメント
なお、webページの末尾にディスカッションの欄がありますので、ご意見、ご批判、ご同意など書き込んでいただければ幸いです。
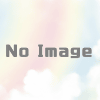



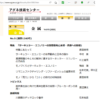
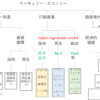
ディスカッション
コメント一覧
原田さんの考え方におおむね賛成です。エコデザインが製品に環境性能を設計で作り込むこと(2009)から、それに加えて、バリューチェーン全体で環境持続性を高めるようにライフサイクルマネジメントと統合的に扱うことを求めるように変化していることは気付いていたのですが、後者を輸入者、ディストリビュータ、ディーラーなどが実施し、それらのステークホルダーも今回のエコデザイン2022枠組みが対象としていることに気付きませんでした。あとは、原田さんのこの深読みが、どの位、EUの担当者の意図なのか。使用価値での競争が市場の主流になるのか。この流れだと、早晩、デジタル製品パスポートに、輸入者、ディストリビュータ、ディーラーなどが元となる情報が加わって、デジタル製品・サービスパスポートになるのか。など感じました。ありがとうございました。