資源生産性に優れた豊かな価値循環社会(広域マルチバリュー循環)研究会 活動計画案
1. 資源生産性に優れた価値循環(マルチバリュー循環)とは
製品は、製品そのものの機能価値だけでなく、ブランド価値、構成部品価値、部材価値、素材価値など多様な価値を含んでおり、多くの場合製品機能の停止をもってライフサイクルが閉ざされそれらの価値は埋もれてしまうケースが多いが、実は残存価値として引き出される価値は残っています。現在それを引き出しているのは素材リサイクルですが、より多様で多階層の残存価値引き出し行為が展開され、それを最終的に支えるものとして素材リサイクルと廃棄物処理が社会インフラの一部として存在すべきです。このような多様で多階層の残存価値を引き出す循環をマルチ・バリュー循環と定義します。
2. ものつくりアジア版サーキュラー・エコノミーへ
現在欧州ではResource Efficiency(資源効率)のアクション・プランとしてCircular Economyが打ち出され、循環型社会へ向けたソリューションというよりもむしろ、横断性に富み残存価値活用に優れたビジネス・マネージメント・モデルとして広く定着しようとしています。
しかし、他方でその循環モデルは、ものづくり能力の地位が相対的に低下してきたヨーロッパの中での製品の再循環モデルに偏重しがちで、アジアをはじめとする生産力をシステム境界外に置いたヨーロッパ・ファーストになりかねない弱さも持っています。
21世紀は資源と環境の制約がますます厳しくなる世紀であり、その中で多くの人々が豊かさを享受できるようにするには、資源の採取から廃棄に至るライフサイクルでのモノの価値を多様に組みつくし効果的に活かしきるマルチ・バリュー循環が求められます。そしてそれは国境を越えて広域で展開し、モノづくりと密接に結びつく必要があります。
3. 推進する中核の形成を
現在、多くの会社や団体、組織が国際的な観点からもSDGsに向けた取り組みを推進しようとしており、そのなかでサーキュラー・エコノミーへの関心を高めています。しかし、それを超える取り組みを意識しても、単独ではサーキュラー・エコノミーの実態さえ把握するのが困難で、ましてや日本の特長を生かした積極的発信を準備するには多くの困難があります。そこで、単に欧米の動向をキャッチアップするだけではなく、この「マルチバリュー循環」というコンセプトを深め、実践の課題や政策として具体化していく研究会をもち、そこを連携の場としていくことで、長期的には国際的に「マルチバリュー循環」を推進していく中核づくりを目指していきたいと思います。
4. マルチバリュー循環研究会の目的
マルチバリュー循環研究会は、次のことを目指します
a) 次世代のグローバルな循環型社会として「広域マルチバリュー循環」のソーシャルビジョン、ビジネスビジョンの鮮明化を図ります。
b)「広域マルチバリュー循環」を実現していくためのバリアの明確化、政策的課題の抽出、技術的ブレークスルーポイントの鮮明化をはかります。
c) JST未来創生研究「リマンを柱とする広域マルチバリュー循環の構築」などの国の施策や技術開発と連携を図り、情報を交換し、研究の最先端を企業に、企業の長期的ニーズを研究にフィードバックする場を作ります。
d) 各企業や消費者、経済主体における「マルチバリュー循環」の実践課題の鮮明化を図ります。
e) そのための先行事例、萌芽事例を見つけ出し、普遍化、普及、宣伝します。
f) 「マルチバリュー循環」を国際的に推進するための政策的課題を明確化します
g) 上記を推し進めようとする企業、団体、個人のネットワークをつくり連携を促進します。
5. 広域マルチバリュー循環研究会の具体的活動
メンバー・ミーティング
会員とオブザーバーで構成されるディスカッションを必要なゲストも招きながら行い、マルチバリュー循環やサーキュラー・エコノミー等の国際動向に関する議論を「攻めの議論」「守りの議論」「俯瞰的議論」として深化させ、政策や実践に結びつける方向を探ります。
「攻めの議論」として、
リマン・サポート技術、プラの長寿命化・信頼性などMVCを支える技術情報の収集や開発促進
広域循環に関わる先進技術情報の整理やシステム要件の経験からの学習
残存価値・信頼性の定量化、表現手法、標準化へ向けた議論
広域マルチバリュー循環にかかわる実施例や新構想
「守りの議論」として、
欧州・中国などの税、規制、標準化、認証などの政策的動向
「俯瞰的議論」として、
環境容量、資源効率に関する最先端の情報の学習
CEなど各地域の物質循環、価値循環に関するアプローチの情報収集と議論
ビジネス・モデル検討会 (ディープ・ディスカッション)
幹事団体およびその承認を得た指定メンバーによる、広域マルチバリュー循環のビジネスモデルの検討会、複数口会員を優先
コンジョイント・ミーティング
連携学協会との共同ミーティングを行う
メンバー議論は当面は分野ごとに分けるのではなく、数カ月に一回設定し、会員の持ち回りで主査会員を定め、主査会員が上記の中からテーマを決め、事務局とともに講師や話題提供者を準備する。
メンバー議論での内容は秘密保持とするが、メンバー議論のテーマと許可を得た講師の講演内容は公開することがある。
会員もしくは会員により指名されたものは無料で参加できる。(指名は事前に幹事の了解が必要)
オブザーバーは主査会員の了解のもとで無料で参加出来る。
公開シンポジウム
シンポジウムを企画し、「広域マルチバリュー循環」に関する先進例の紹介、および関連する国内外の動きに関する議論を公開して行う
公開シンポジウムの企画は代表と幹事で行ない、実行は事務局がすすめる。
会員もしくは会員により指名されたものは参加登録費を免除される。なお、資料代、交流会代等は別。
エンブリオ・ミーティング
エンブリオ(embryo)とは物理学では物事のもとになる核が形成される前の段階を指す。広域マルチバリュー循環を進めるうえで、新しいコンセプトに基づく新しいコラボレーションの準備の場を作る。
複数の会員が特定のコラボ関係が形成できる可能性がある場合に、そのいずれかの会員の意思もしくは幹事やオブザーバーの意見に基づいて、クローズドの会合を斡旋します。その斡旋を受けるか断るかの権利は当該会員に帰属する。
両会員の合意の下で幹事等が同席し、周辺環境の調整などの可能な協力をおこなうことがある。
内容の公開は不必要だが、斡旋件数だけは会のアクティビティの指数として把握。また、「広域マルチバリュー循環」の普及の視点から、可能な成果・情報の会へのできるだけの還元を行う。
マルチバリュー循環および関連する動きに関する情報収集、調査。
単数もしくは複数の会員が協力して必要資金を供出し、それが本会の目的と合致するならば、「広域マルチバリュー循環」および「資源効率」に関わる国内外の調査を行うことができる。
調査を行う主体は申し出会員の意思を尊重しつつ幹事が指名する。引き受ける主体が見つからない場合は調査は成立せず、資金提供も不要となる。
「広域マルチバリュー循環」および各企業の先進的取り組みの普及、公報
将来、会員が増加し事務局機能をより強力にすることができたならば、積極的に取り組むが、当面は、a)メンバー議論を中心に、b)公開シンポジウム、c) エンブリオ・ミーティングに重点を置く。
その他マルチバリュー循環および関連する動きに関すること
6. 会員の性格、体制等
会員制をとり、企業、団体、組織のユニット単位もしくは個人の正会員と、幹事団により推薦された特別会員(オブザーバー)および幹事団と事務局で構成する。
組織のユニットとは企業等目的追求型の組織においては会社を最大単位とし、それをホールディングスのような系列化でくくることはできない。また最小単位は、組織分掌にもとづいて細かくしても構わない。
組織のユニットは、大学や官公庁のようなデパートメント型の組織においては、課、グループなど同一の目的や分掌をその単位とする。
会費はユニット単位および個人を問わず年間10万円を一口とする。それぞれのユニットから登録された構成員は会員として口数に合わせた権利を有する。
なお、幹事を出した会員組織は、年会費を一口免除、もしくは減額することができる。
特別会員(オブザーバー)は、本会に必要な知識や情報の提供もしくは活用を期待される個人、および本会の目的に合致する公共性の行政関係など公共性の強い組織とする。
年間報告書を購入予定の団体は準会員扱いとできる。準会員は議決権を有さないが会のミーティングなどの取り組みに会員と同等の条件で参加できる。
会は関連する学協会と相互の理解のもとに連携し、それを連携学会と呼ぶ
オブザーバーは年会費を払う必要はない。また会の運営に関して責任を負ったり権限を行使することはない。
オブザーバーは会のメンバー・ミーティング、公開シンポジウムに無償で参加することができるが、交通費などの補助は基本的に行わない。
会員および個人メンバーからえらばれた幹事団を形成し、運営にあたる。
事務局は(一社)サステイナビリティ技術設計機構がうけもつが、「マルチバリュー循環研究会」のための事務局員を雇用する。
6 運営
年に1回総会を開き、活動方針の概要を決定する。会員は口数に応じた決議権を有する。
会の活動の執行は事務局を中心に行う。
年に数回幹事会を開催し、活動内容を検討する。幹事会は基本的に企画行事の一部と合わせて行うが、インターネットを援用する場合もある。
7. スケジュール案 (1年分)
6月21日 正式発足 発足会・総会と記念シンポジウム(第一回公開シンポ)
7月中旬あたり 第一回 メンバー・ミーティング 例: リマンを支える技術開発
8月下旬あたり 第二回 メンバー・ミーティング 例: 欧州の環境規制の変化について
11月中旬あたり 第三回 メンバー・ミーティング 例: プラスチックの長寿命化とリサイクル
1月中旬あたり 第二回公開シンポ 例:リマンとマルチバリュー循環
2月下旬あたり 第4回 メンバー・ミーティング 例: 発展途上国の価値循環
4月中旬あたり 1周年 総会・公開シンポ 例: わが社のマルチバリュー循環への取り組み
2018年5月28日
資源生産性に優れた価値循環社会(広域マルチバリュー循環)研究会
呼びかけ人代表者 原田幸明 物材機構 名誉研究員、サステイナビリティ技術設計機構代表理事
呼びかけ人 (あいうえお順)
粟生木千佳 (公財)地球環境戦略研究機関 持続可能な消費と生産領域 主任研究員・プログラムマネジャー
今井 佳昭 リバーホールディングス株式会社執行役員
梅田 靖 東大教授
神崎 昌之 (一社)産業環境管理協会LCA事業推進センター所長
喜多川 和典 財団法人日本生産性本部エコ・マネジメント・センター長
小島 道一 ジェトロ・アジア経済研究所 上席主任調査研究員
醍醐 市朗 東大 准教授
高木 重定 みずほ情報総研株式会社環境エネルギー第1部持続型社会チーム課長
田島 章男 パナソニックETソリューションズ(株) 企画・法務部
中島 謙一 国環研 主任研究員
則武 祐二 リコー経済社会研究所 顧問/主席研究員
林 明夫 JFEスチール 社友
林 秀臣 エコデザイン推進機構理事
廣瀬 弥生 財団法人電力中央研究所 企画グループマーケティング担当部長
松本 光崇 産総研 主任研究員
村上 秀之 物材機構 グループリーダ
山末 英嗣 立命館大学 准教授
活動計画案はこちらからpdfダウンロードできます
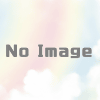


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません